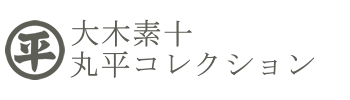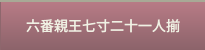馬上の大将 高さ75cm
十二世面庄木彫頭 五世大木平蔵作 本体・頭共に大正末期作
丸平の五月人形史上でも特筆すべき名品で、白馬は木彫りでヤマナという職人の作。もっと手頃な紙製の馬を作っておられた横尾さん共、既に馬職人は京都から絶えました。馬の表面は、胡粉塗りが生乾きの時に猪牙(チョキ)で引っ掻いて毛並みを描き、胡粉の置き上げによって血管をも浮き出させます。甲冑の飾り金具は、銅板をくり抜いて彫り出す地彫り(ヂボリ)という工法で、そこに水銀を塗り金箔を押した後に燻り出して定着させる、けし鍍金という工法。燻り出る気体を職人が吸い続けると水俣病のようになるとか…現代では禁じられた鍍金法です。類い希な緋縅(ヒオドシ)の紐。凝った太刀、鉄製の鐙(アブミ) 、木彫漆蒔絵の鞍等々の小道具。面庄作木彫一品物の頭には、絹スガ糸を羽二重に植えた髭を貼り付けるという凝り方、どれを取っても上等尽くしの逸品です。尚、これにはもう一頭“鞍置きの馬”と呼ばれる、大将の乗る白馬が潰れた時に乗り換えるために鞍だけを置いた栗毛の馬が付きます。何人かの従者を従えていたのかもしれませんが、金屏風の前に単体で据えた時の一際凛とした姿こそ、この人形の真価ではないでしょうか。
























特別寄稿 『馬上の大将』人形研究家 林直輝
端午の節句に飾る人形は、江戸時代以来、歴史上あるいは伝説上の英雄豪傑の姿を表すことが主流であった。それはその人形が武威を以て邪気をしりぞけ、男児の健やかな成長を祈念するにふさわしいからに他ならない。しかるに戦後、そのような武者人形はほとんど影をひそめ、現在では老舗といわれる人形店でもわずかに鍾馗と神武天皇の人形を見かける程度となってしまった。店頭には時代も人物も不特定の、単に可愛らしさのみを狙った子どもの人形が並んでいる。
その変様は、昭和戦後の歴史教育のゆえとも、戦中の軍国主義への反動ゆえともいわれるが、かつての武者人形の多くが歴史的事実というよりも古典文学や説話に取材したことを思えば、それはむしろ現代人の「教養」の問題によるところが大きいのではなかろうか。今日まで百年一日の如く伝統を堅持する丸平でさえも、人形司としての暖簾を掲げる以上、需要なき武者人形を作り続けることは難しかったのである。
そうした意味において、五世丸平の「馬上の大将」は、生まれるべくして生まれた、時代の傑作である。近年、明治時代の各種美術工芸にみられる「超絶技巧」への再評価が進んでいるが、顧みて昭和初期もまた、その優れた技術を受け継ぎ、さらに感覚的な洗練をも加え得た恐るべき時代であった。国民間の貧富の差が激しければこそ、「持つ者」の財力は尋常ではなく、現在の価値にして数億円を節句飾りにつぎ込む富豪さえ存在したのである。いかなる名工といえども、民芸(民衆的工芸)ならぬ伝統工芸の分野において優れた作品を作ろうとすれば、材料と手間の点から多大な経費のかかるのは当然である。作る者と求める者、その両者が揃った昭和初期は、史上まれにみる美術工芸の黄金時代であった。そして、この馬上の大将こそはまさしくその精華といえるであろう。
馬上の大将の「大将」とは、節句人形においては「文武にすぐれたる者」という程度に解釈され、特定の誰かである必要はない。ただし、江戸から昭和にかけての京都製の武者人形の作例をみれば、それが主として源氏の大将・八幡太郎こと源義家をイメージしたものだということは容易に知られよう。本作も赤地錦の鎧直垂に赤糸威の大鎧を着し、笛籐の弓を持ち、大和鞍を置いた白馬に乗るという典型的義家像ではあるものの、仔細にみるほどに、同じく丸平による他の馬上の大将とは別格の作品であることが明確となってくる。(あえて断っておくが、馬上の大将に限らず、丸平の人形というものは、いかなる並物であろうとも、他の京人形司を自称する者たちのおよそ及ばぬ美意識に貫かれており、通常商われた馬上の大将でさえも、すでに節句人形としての最高峰に位置しているのである。)
本作の特徴として、武具甲冑に関してかなりの知識を有した者の関与がうかがえる。もっとも、平安時代の武将である源義家の姿を忠実に再現しようとしたのならば、大鎧の様式も、太刀の拵も後代のそれであり、大立挙の脛当など、時代考証的には誤りというべき表現が多々認められるのであるが、本作はもとよりそうした学術的意図を離れて製作された節句人形なのである。つまり、歌舞伎のヒーローと同様に、あくまで物語のなかの義家を描きつつも、そこに近代の有職故実研究の成果をほどよく採り入れた、知的な芸術表現とみることができるのである。
さらに重要な点は、節句人形として欠くべからざる祝賀の趣を表現していることである。本作においてそれを可能としたのは、何と云っても馬の三懸の赤糸、大鎧の威糸、そして金工である。絹糸の艶やかさはそれだけでも充分に美しいが、ここでは三懸の総としてふんだんに用いられ、その質感を一層際立たせている。この「惜しげのないふんだんさ」は、コスト優先でものづくりをする一般の人形店では到底叶えられない。威は組紐そのものの良さに加えて、札板への紐の通し方が見事で、一段ごとにふっくらと浮き上がるかのようである。精緻な飾金物は本物の甲冑においてもひとつの見所であるが、通常の節句飾りでは、そのほとんどが量産可能な鋳物である。しかし、本作では金属板をじかに彫りあげた地彫の金物を配しており、贅沢この上ない。先述のように、この大鎧は義家在世中の平安時代の様式ではなく、鎌倉時代の遺品や江戸時代後期に大名家で儀礼用に誂えた復古調大鎧に近いものであるが、時代考証を超越して、あえてこの表現を採った主な理由も、おそらくはこの金物多用による華麗さにあったと考えられるのである。
翻って、大将の乗る馬に着目すれば、これは節句飾りの「飾馬」の応用である。ただし、一般的な飾馬にしては巨大に過ぎるので、むろん既製品の転用ではなく、本作のために作られたものである。あえて応用と云ったのは、作者がこの馬を手掛けるにあたって、どれほどの経験を積んでいたかということに思いを馳せたからである。大きさからいっても細工と云うより彫刻の範疇に入るものであろうが、出来上がった姿は彫刻的リアリズムではなく、まさに人形の世界の様式美なのである。したがって、作者はきっと普段の飾馬と同じ手順で仕上げたはずだが、こんな大きな馬を何の苦もなく作る職人が存在したというのも、かつての京都の恐ろしさである。
ところで、「人形は顔がいのち」といわれるが、本作ほど顔を意識させない節句人形も珍しいのではあるまいか。一見して甲冑の美々しさや馬の迫力に圧倒されるためなのは明らかだが、そうした印象は案外、実際の軍陣における武将の姿に近いとも考えられよう。とはいえ、不世出の名工・十二世面庄(面屋庄次郎)による本作の頭は、いかにも京好みの端整にして気品高い面立ちであり、しかも髭は一本ずつ植毛する精巧さである。作品全体の豪華さに驚嘆した後、兜の眉庇深くを窺えば、まさしく御大将というにふさわしい容貌なのだから、感動もまたひとしおである。
本作は五世丸平の傑作と云うにとどまらず、昭和初期の美術工芸の粋を集めた、節句人形の到達点を示す比類なき逸品である。染織、金工、彫刻と、今日ではその全てが望むべくもないが、斯界に携る方々にはせめてこれを軌範とする良心だけは忘れてほしくないものである。
源三位頼政賜御劔(ゲンサンミヨリマサミツルギヲタマワル)
高さ62cm
2015.12に突然ヤフーオークションに登場したこの人形は、恐らく五世大木平蔵時代に作られた別格中の別格である五月人形だったはずなのです。しかし、いったい何の場面を題材にした五月人形なのか、まるで分からないのです。
十二世面庄による頭は、或いは木彫り一品物ではないかと思う紛れもない名品ですが、見たこともない伏し目に作られていて、取り分け口元に見て取れる得も言われぬ色香といったら!
深紅の単は板引。半臂まで着込めた脱ぎ着せ仕立ての装束は何と夏物ではありませんか。以前から夏物の装束での丸平男雛を夢見ていた私ですから、これを発見した時には仰天してしまったのです。単(ヒトエ)のみならず、厚手の紗(シャ)での装束は全てが捻り仕立てにされていました。闕腋袍も半臂も同一の生地ですので、藍色と渋い金茶というプランで染め分けたのでしょう。さすがの配色だと感嘆してしまいます。
この人形は、どうしたわけか人形にあるまじき短い腕でしかなく、それは袖の中で手の平を上に向けて前に差し出しているだけなのです。失われたにせよ、それが何だったのか全く不明なのですが、何の持ち物も残されていません。五世平蔵時代には『源太の産着』と題する五月人形が幾つも作られていて、寸法帳には半臂の寸法まで残されているというので、最初は八幡太郎義家が生まれた時、その父頼家が我が子を鎧の片袖に乗せて参内したという逸話による五月人形かと思ったのですが、そもそも鎧の袖なのですから、両側から引っ張りでもしない限り、差し出しただけの両腕だけではずり落ちてしまうのです。ましてやその上に赤ん坊を載せるなど無理な話なのです。それを人形ならではの嘘として譲ったにしろ、あまりにも頼家の目の前に赤子の顔が寄ってしまうのです。すると、何故しかめっ面とも見えてしまうほどの表情にしたのか、まるで説明が付かないのです。私にはどうしても『源太の産着』だとすることが出来ませんでした。
直接手に触れないように持たなければならない何かならばと、捧げ持たれる三種の神器の剱を思いつき、太刀を入れた箱と袋を仕立てて持たせてみると、それを見せた中世文学専門の友人が、鵺(ヌエ)退治によって御所で御劔を賜ったという源三位頼政のように見えるというではありませんか。ならばと、異常に短い手に2寸ばかり腕を付け足して手の平を袖の外に出し、それに御劔を持たせてみたのですが、それを見た五月人形研究者の友人が『これで決まり!』と絶賛されたのです。五世平蔵時代にどんな人形として仕立てられたにしろ、それを超えた最良の形として、百年も過ぎた平成の世に甦ったのではないかとまで言われたのです。
しかしながら、これは決定ではありません。証拠がないのです。それで丸平さんが誂えてくれた箱は、箱書きを躊躇ったまま、今でも白木のままなのです。
尚、冠に付けられているのは『菖蒲の蔓』で、『九暦』に記されている寸法を人形のサイズに合わせて縮尺復元したものです。
挿頭花として、藤と卯の花も作ってみました。










神武天皇 高さ62cm
十二世面庄練頭 六世大木平蔵作 頭明治~昭和初期作
戦前、現代では考えられない程多種多様な五月人形が作られました。多くは日本神話や歴史上の武勇伝に取材され、神武天皇もその一つです。この大きな立像は、丸平さんで作られた最後のものでした。敗戦後の混乱期が最も経営維持に困難だったという丸平さんにとり、男の子が生まれるたびに一体ずつの神天立像を注文された岡山の方には随分と助けられたとか。三体の注文が続いた時、この様子だと…と余分に一体作り置いたものの注文が来ず、蔵に残されたものです。戦後はすっかり五月人形が廃れ、今でも丸平さんには武内宿彌、太閤秀吉、家康、大久保彦左衛門、乃木大将、明治天皇といった様々な面庄頭が大量に残されています。そもそも神武天皇など架空の人物ですが、古代の人物として装束は左前の着付けです。やなぐいは細い籐で編んだ精巧な物で、三十数本の矢は櫟井(イチイ)の小枝で作られています。どなたの仕事でしょうか、みづらの結髪も非常に端正です。






子供馬乗り大将
十二世面庄作の子供頭は、可愛らしいながらも凛々しく品格に溢れ、さすがに追随を許さないものがあるように思います。
鎧兜は朱色の縮緬貼りで、名工ヤマナ作の馬もまた縮緬貼りでした。
左手には定番の弓を持っていたのでしょうけれど、既に失われていたため、色彩のアクセントからも、寒色の菖蒲を持たせてみたのです。
丸平の五月人形としたら、特別なランクでもない品物なのですが、丸平・十二世面庄・ヤマナのトリオというだけで、この上ない価値に舞い上がって手にしたのでした。




末廣がり 高さ30cm
初世川瀬健山作本狂八寸石膏頭 七世大木平蔵作 頭昭和40年代
“本狂い”とは、五世平蔵時代の創作人形と言うべき三頭身程の衣装御所人形で、本来の寸法狂いという意味とか。尺六寸やら大きな物まであります。三番叟や竹生島など多くは能や狂言をテーマとして、衣装には凝った刺繍を施しますが、この「末廣がり」の布地は、五世時代に刺繍までされて残されていたもので、端正で達者な刺繍技術にもかかわらず、決して特別の品というわけではないのです。
この頭は二世猪山の型により、初世健山が仕上げた石膏頭です。驚くべき事に、丸平さんには十二世面庄による木彫り本狂い九寸頭がいくつも残されているのですが、需要が多かったからでしょうか、八寸頭は一つも残されていず未だ心残りでいます。